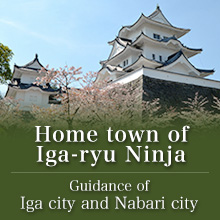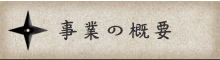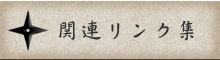忍者のナンバープレート
伊賀市と甲賀市が県域を越えた連携事業として取り組んでいる忍者のデザインが入ったご当地ナンバープレートの交付枚数が、昨年4月2日の開始から1年間で伊賀市819枚、甲賀市622枚の計1441枚だった。


交付対象は排気量が50CC、90CC、125CCの原付バイク。ナンバープレートはオリジナルと既存で選択できるが、伊賀市では昨年1年間で867枚を交付したうちの約94%が、甲賀市は1043枚のうち60%がご当地ナンバーだった。
忍者の里という観光資源で一致することから、甲賀市側から同事業を提案。ナンバープレートのデザインは公募し、計193点の応募があった。
同事業以外でも、両市間では職員の人事交流などで連携協力している。
平成13年4月 you掲載
鈴降稲荷神社

鈴降稲荷神社は、港区赤坂にある稲荷神社です。鈴降稲荷神社は、本能寺の変に際して徳川家康が大阪から三河へ逃れる際、伊賀山中で観音堂の堂主山名孝倫から厨子に納められていた三箇の鈴を受領、無事浜松に戻れたことから、江戸開府後に伊賀の領民を四谷に住まわせて伊賀町(伊賀組)の鎮守社として創建したといいます。元禄8年社地が御用地となり当地へ遷座、大正14年に赤坂氷川神社境内の四合稲荷神社へ合祀されたといいます。
http://www.tesshow.jp/minato/shrine_akasaka_suzufuru.html
http://iihi-tabidati.blog.so-net.ne.jp/2012-03-11
明屋敷伊賀者組頭格 内田弥太郎
明屋敷伊賀者組頭格 内田弥太郎
嘉永元年4月より明屋敷伊賀者から浦賀奉行手付となった内田弥太郎は、明治政府に出した経歴書に異国船来航時に手伝ったとあったが中々記録が見つからなかった。『南浦書信』嘉永6年12月2日の戸田氏栄が井戸鉄太郎に出した書信にようやく内田の記録があった。戸田は井戸に対して内田の手当金の増額の要請を行っている。明屋敷とは今の幕臣の空いた屋敷を管理する警備人のような仕事である。若くして和算家として名声を得ていた内田弥太郎にとっては戸田伊豆守氏栄と下曾根金三郎による浦賀での抜擢は非常に感謝していただろう。下曾根は南町奉行・筒井政憲の実子でまた戸田氏栄3男は筒井のあっせんで長井家へ養子となった。内田弥太郎の和算の弟子にあたる花香恭法に戸田氏栄5男鉄丸(花香恭次郎)を世話した理由と思われる。
http://blog.goo.ne.jp/tukemaru/e/d55a86e985ae7ccf21e90edae178cef5
伊賀坂

【標識(文京区教育委員会設置)の説明】
白山台地から白山通りに下る坂で、道幅は狭く、昔のままの姿を思わせる。この坂は武家屋敷にちなむ坂名の一つである。
伊賀者の同心衆の組屋敷があった(『御府内備考』)とか、真田伊賀守屋敷があった(『改撰江戸志』)という二つの説がある。
『東京名所図会』では真田伊賀守説をとっている。伊賀者は甲賀者と共に、大名統制のための忍者としてよく知られている。
http://www.tokyosaka.sakura.ne.jp/bunkyoku7-nishikatahakusan.htm
伊賀町
東南端の土堤上は築地屋敷と称し、そこに伊賀の忍者衆が居住したので町名となった。(『日本歴史地名大系第24巻 三重県の地名』)
http://blog.goo.ne.jp/rekishi_tabi/e/12e55458a969bdd9fc7ffc6452db60c7
服部家住宅

服部家は、伊賀国服部郷の出身で、南北朝以来、上服部家の統領は、伊賀守(いがのかみ)を名乗っていました。
http://www.aichitabi.com/yatomi/hatori.html
笹寺
伊賀組同心のストライキ
徳川家康の艱難辛苦に満ちた生涯を表から裏から支え続けた服部半蔵正成は、関ヶ原の合戦を4年後に控えた慶長元(1596)年、55歳でこの世を去りました。
正成亡き後、嫡男の正就<まさなり>が半蔵の名と、父の遺領8,000石のうち5,000石、それに与力7騎、伊賀組同心200人を受け継ぎました。
ところが苦労人の父と違って、生まれながらの大身旗本であった正就はわがままで粗暴でした。家康の異父弟で伊勢桑名(三重県桑名市)11万石の城主だった松平(久松)定勝<さだかつ>の娘、つまり家康の姪を妻に迎えたことも、彼をいっそう増長させたのかもしれません。
正就は自分の屋敷の普請をするのに、伊賀組同心たちをまるで下僕のように扱い、労力ばかりか材料まで提供させました。従わない者には、給料に当たる糧米<かてまい>を減らしたり、払わなかったりしたのです。
もともと同心たちは徳川家に召し抱えられたのであって、服部家の私的な家来ではありません。当然、彼らは反発しました。正就と折衝することも試みましたが、一向に埒<らち>があきません。正就は話を聞くどころか、反抗する者には私刑をもって臨むといった有様でした。
慶長10(1605)年秋、彼らの怒りがついに爆発します。弓・鉄砲を揃え、200人が四谷の笹寺(ささ寺)に立て籠りました。ストライキを敢行したのです。
彼らの要求は、正就の罷免と与力への昇格、それに扶持米のアップでした。もし訴えが容れられなければ、斬り死にする覚悟だったといいます。
もちろん、彼らの要求がたやすく通るわけがありません。幕府は旗本に命じて笹寺を包囲させました。ところが、そこはさすが忍者です。寺を抜け出しては食料を調達するために市中を荒らし回ったので、江戸の治安は大いに乱れました。
ようやく幕府は重い腰を上げ、事実調査に乗り出します。その結果、伊賀組同心の言う通りであることがわかりました。そこで正就を罷免し、同心たちを大久保忠直ら4人の旗本に分けて所管させました。
一方的に処罰されて、憤懣やる方ないのは正就です。彼は首謀者10人の処刑を要求しました。
確かに徒党を組むことは幕府の規則に違反しますし、市中を荒し回った盗賊まがいの行為は許されることではありません。8人はあえなく打首となりましたが、2人が逃亡してしまいます。
執念深い正就は彼らを探し回り、そのうちの1人らしき人物を見かけて後を追い、斬り殺してしまいました。
ところが・・・、なんとこれが、人違いだったのです。
しかも悪いことに、正就が斬ったのは、関東代官頭を務め、徳川幕府による地方支配の基礎を築いた功労者伊奈忠次<いなただつぐ>の家士でした!
ことここに至って、ついに服部家は分家だけを残して改易となってしまいました。
同心たちが立て籠った笹寺は、正しくは四谷山長善寺(東京都新宿区四谷4-4)といいます。
笹寺という呼び名は、2代将軍徳川秀忠が鷹狩の途中に立ち寄った時、境内に笹が繁っているのを見てつけたのだそうで、こちらの方が正式名称よりも浸透しています。
地下鉄丸ノ内線の四谷三丁目駅を出て、甲州街道を4丁目方向に進むと間もなく、左手に寺への入り口を示す門柱がありますが、そこにも「曹洞宗四谷山 笹寺」と彫られています。

http://blog.goo.ne.jp/rekisisakka/e/3378d06545fe2afb47ff80e2bb8a748c
服部半蔵奉納の仁王像

宝永3年(1706)銘。伊賀衆の服部半蔵が、付近にあった高松寺(廃寺となっている)に寄進したものです。
徳川家康より伊賀衆に橋戸村・白子村の一部(現在の大泉周辺地域)を給地されたことに関する資料としてばかりでなく、区内にある仁王像の中でも優れた出来映えの石造物です。
平成4年(1992)3月 練馬区教育委員会
http://tokyonerima.blog.shinobi.jp/Entry/35/
伊賀町(備中高橋)
「伊賀町」は.頼久寺町と向町が交わる龍徳院前の踏切付近から,紺屋川の右岸を奥万田、楢井方面ヘと登る坂道(楢井坂)に沿う細長い町で、秋葉山の南麓に位置する町であります。
池団長幸が.元和3年(一六一七)に入国し、下級武士の屋敷地としてつくったと言われる城下町時代の「伊賀丁」が、そのまま、「伊賀町」地名として残っているものです.「伊賀町」を石川時代(一七一一~四四)の絵図(「松山城下絵図」・亀山市図書館)で見ると、道の南側に沿って百人組長屋と家中屋敷三軒や明地が、北側に矢場と梅岩寺、長州寺の二つの寺が描かれています。
また、延享元年(一七四四)、には、家中屋敷二.給人屋敷一、一棟長屋三が記録(「松山家中屋敷覚」=市図書館)されていて、この町の様子も移り変わっていることが分かります。
「伊賀町」は楢井坂を下って城下ヘ入る東の重要な入口だったため、奥万田口ヘ城(木)戸を設け、城(木)戸番を置いて警固をしていたようで.この地区に伊賀者(しのびの者)を住まわせていたところから、伊賀町」といる地名がついたのであります.当時、伊賀者がどんな生活をしていたのか分かりませんが、華やかな、江戸初期に比べ、、江戸時代後半になると、ただ単なる門番などの雑役が多く、三人扶持ぐらいの薄給だったようで.忍者の時代は終わっていたのであります。
この町は、幕末の天保十年(一八三九)の大火で焼け、その後、町も様変わりをして近代へと移り変わって行きます。明治十四年になると家中屋敷や矢場の跡地に岡山県下初の女学校がつくられ、その後、明治四十、一年に順正女学校がこの地に移ってきて、現在は、「順正寮跡」と」て残っています.「伊賀町」という地名は皇居の内にある「百人長屋」や「半蔵門」。そして.東京の「笄町(こうがいちょう)」(甲賀、伊賀の略).三重上野市の「忍町」などと同じ城下町地名なのです。
http://ftown.chu.jp/wi/wiki.cgi?page=%B0%CB%B2%EC%C4%AE
荻窪
≪荻窪の由来と伊賀忍者≫
荻窪の由来は、地名発祥由来の寺と言われている「光明院・杉並区上荻2-1-3」 に残っています。
当時の記録によると、和銅元年(708年)一人の修行僧が観音様をおぶって この地を通ると、不思議にも尊像、急に重くなり、歩くことが出来なくなって しまいました。
修行僧は尊像はこの地に縁があるのではと思い、付近一帯に自生していたオギ (荻・イネ科の多年草)という草を刈り取って草堂を作り、観音様を安置し草堂 を荻堂(荻寺)と名付けました。
また、この周辺は窪地だったことから、荻と合せて、荻窪と言われるように なったようです。
鎌倉時代から室町時代に至る動乱期には豊島郡に属し、文明9年(1477年)に豊島氏が上杉氏の家宰(補佐)である太田道潅に滅ぼされるまでは豊島氏の 領地で、その後は北条氏、徳川氏の領地となりました。
江戸時代の初期、荻窪から西荻窪の全域は伊賀忍者の知行地(俸禄として与えられた領地)があったそうです。
その昔、荻窪村は京都に近い西側を上荻窪村(現在の西荻南・北、上荻、 南荻窪東側)、遠い東側を下荻窪村(現在の荻窪と南荻窪西側)の2つの村に 分けらていました。
下荻窪村は伊賀忍者の棟梁服部半蔵の知行地に、上荻窪村は伊賀同心八名の知行地にしたようです。
伊賀組
伊賀組組頭・服部仲の組屋敷だったことから四谷仲町となった。
元禄の地震による火事の後は仲殿町と御駕籠町となった。
伊賀組(いがぐみ)は江戸幕府における百人組の一つ。百人組は同心百人が配属されたことから鉄砲百人組とも称される。長は組頭と称した。伊賀組は神君伊賀越えの際道中を警護した伊賀忍者の子孫から構成され、江戸城大手三門の警備を担当し、甲賀組、根来組、二十五騎組とともに百人番所に詰めた。組頭は服部仲など。組屋敷は四谷仲町、後に伊賀町に与えられていた。
伊賀町
昔の公図等を見ると、当時の小屋町に小字で伊賀という地名があります。春日岡城の周辺にはお城に仕えた武家達の屋敷があって、伊賀に縁のある侍(小姓)が屋敷を構えていた辺りが、地名として現在の町名に結びついたと考えられます。
http://www.city.sano.lg.jp/profile/chimei/iga.html
伊賀八幡宮
氷川神社
江戸時代から明治の中ごろまで橋戸村といった。ほとんどが幕府直轄の村ばかりあった練馬区内としては、数少ない私領で、忍者服部半蔵率いる伊賀組の給地であった。その伊賀衆奉納の御手洗(みたらし)が氷川神社(大泉町5-15)境内にある。地名の起こりは、村の開発者が八戸あったからとする説もあるが、白子川の地形がつくる「端の瀬戸」と解した方が妥当のようだ。 明治22年小榑村(こぐれむら)と合併、埼玉県榑橋村(くれはしむら)となり、同24年東京府へ編入、大泉村大字橋戸といった。昭和7年市郡合併で板橋区になったとき、大泉村は東・西・南・北大泉町と大泉学園町の五つに分かれた。旧橋戸村は北大泉町と呼ばれた。昭和22年練馬区成立後も町名はそのままだったが、55年住居表示が実施され北をとって今の町名になった。北端(きたはし)のイメージをぬぐい去って、町発展の期待がこめられているのだろう。 清水山憩いの森(大泉町1-6)のカタクリ、八坂神社(同1-44)の富士山、大泉第一小学校(同3-16)正門脇の御鷹場の碑、人頭石で有名な教学院(同6-24)など、町内には史跡が多い。
ねりま区報 昭和59年8月1日号 掲載

https://www.city.nerima.tokyo.jp/annai/rekishiwoshiru/nerimanochimei/hokusei/ima_ooizumimachi.html
笄町
町名の「笄」とは女性の日本髪に用いられた「簪(かんざし)」と並ぶアクセサリーのひとつであり、名の由来にはそれにまつわるエピソードもある一方、甲賀と伊賀両家の屋敷にちなみ「甲賀伊賀町」転じて「笄ヶ町」から「笄町」となったという駄洒落のような説もある。
https://www.ninja-museum.com/ninja-database/wp-admin/post-new.php
赤目不動尊
この不動尊は、もとは赤目不動尊と言われていた。元和年間(1615~24)万行和尚が、伊賀国の赤目山で、黄金造りの小さな不動明王像を授けられ、諸国をめぐり、いまの動坂の地に庵を結んだ。
寛永年間(1624~44)、鷹狩りの途中、動坂の赤目不動尊に立ち寄った三代将軍家光から、現在の土地を賜わり、目赤不動尊とせよとの命を受け、この地に移った。それから目赤不動尊として、いっそう庶民の信仰を集めたと伝えられている。
不動明王は、本来インドの神で、大日如来の命を受けて悪をこらしめる使者である。剣を持ち、怒りに燃えた形相ながら、お不動さんの名で庶民に親しまれてきた。江戸時代から、目赤、目白、目黄、目青、目黒不動尊は五色不動として、その名が知られている。
目白不動尊は戦災で豊島区に移るまで区内の関口2丁目にあった。

http://members.jcom.home.ne.jp/urawa328/meaka.html
半蔵門
江戸城の西側にひときわ深い堀と立派な門がありますが、この堀を「半蔵濠」、門を「半蔵門」といいます。
服部半蔵は、徳川家康の三河時代からの旧臣で、本名を石見守正成といい、伊賀者(忍者)の頭でした。
徳川家と伊賀忍者との関係は、本能寺の変(1582年)の際、徳川家康は服部半蔵など数名の家来を伴い泉州堺(大阪府)を訪れていましたが、急ぎ三河岡崎に帰るためには、敵味方分からない中、敵陣を突破する必要がありました。
そこで、半蔵は、世に云う「伊賀越え」の策を講じました。甲賀・伊賀国境の峠を越えて伊賀の地に入り、割拠し合う地の忍者群をうまく説き伏せ、支援を受けつつ、北伊勢に抜ける。そして、白子浜(現在の鈴鹿市)から海路で、家康の本国、三河岡崎城に無事到着する、というものです。
『徳川実記』には、この伊賀越えを「後生涯御艱難の第一」つまり家康最大の危機であったとあります。まさに半蔵がいなければ家康の命は危なかったのであります。岡崎帰城後、家康は彼らを召し抱え、甲賀・伊賀の忍者を徳川家の隠密団とし、半蔵にその隠密頭の役を命じました。
江戸城の半蔵門は、この服部半蔵の屋敷が門前にあり、半蔵が守っていた門と言われています。
この場所は、甲州街道の起点となっており、甲州方面の敵から江戸城を守るとともに、逆に、戦で江戸城に危難が迫った折には、甲州方面に逃げるという要衝だったとのことです。
半蔵門から甲州街道(今の新宿通)を西に約2.5kmのところに、西念寺があります。

http://www.pref.mie.lg.jp/tokyo/hp/yukari/04.htm
半蔵門駅
半蔵門線(はんぞうもんせん)は、東京渋谷区の渋谷駅から墨田区の押上駅までを結ぶ、東京地下鉄(東京メトロ)の鉄道路線。鉄道要覧における名称は11号線半蔵門線である。
路線名の由来は徳川家康の家臣・服部半蔵正成の屋敷の側にあったことから名が付いた江戸城の門の一つ、「半蔵門」から。車体および路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーは「パープル」(紫)、路線記号はZ。![]()

http://www.tokyometro.jp/station/hanzomon/index.html
http://www.navitime.co.jp/railroad/00000774/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%A1%E3%83%88%E3%83%AD%E5%8D%8A%E8%94%B5%E9%96%80%E7%B7%9A
忍者地蔵

臨済宗系単立寺院の祥山寺は、瑞渓山と号します。祥山寺は、壁誉長老禅師(永禄2年1559以前の人で)が開山となり文禄4年(1595)麹町付近に創建、寛永年間に当地へ移転したといいます。伊賀衆の菩提寺として名高く俗に忍者の寺といったといいます。
http://www.tesshow.jp/shinjuku/temple_wakaba_shozan.html