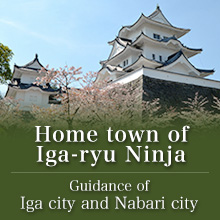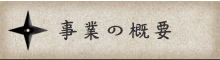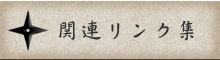Author Archives: NINJA01
萬川集海
延宝四年(1676)伊賀の藤林保武によって著された忍術の三大秘伝書の一つ。 甲賀・伊賀忍術四十九流派の秘伝・忍具を体系的に詳述した忍術の全てを集大成したものである。 1789年に甲賀者によって幕府に献上された。本書には延 … Continue reading
伝達方法
昔の情報の伝達方法は「人から人へ」が基本で、歩く速度と情報の伝達速度は同じであった。そのため、急いで知らせたい情報は、あらかじめ相手と約束事を決めておいて合図で知らせた。合図には、鐘、太鼓、ドラなど音を使うもの、狼煙を … Continue reading
火術・火縄
忍者は火術を得意としていた。鉄砲と共に種子島に火薬が伝来する以前に、すでに甲賀では大陸からの渡来人が火薬を製造していたといわれている。 伊賀と甲賀は、もぐさ、ショウノウ、馬ふんなどの火薬の原料が手に入りやすく、火薬の … Continue reading
睡眠
忍者は、忍びに適した日や、人の「睡眠」についての研究を重ねた。月明かりのない日や、人の眠りが深い日を選んで忍ぶと、発見されずに目的を達成することができるからだ。 敵が熟睡しているかどうかは、「聞き筒」という筒で寝息を聞い … Continue reading
忍者の一日
忍者であることをカモフラージュする為、薬草の栽培、また実益をかねて忍者たちは普段農業に従事していた。そして薬草からさまざまな薬を作るのも日課であった。その中には武器に必要な火薬の製造という大切な仕事も含まれていた。そし … Continue reading
忍者屋敷
伊賀・甲賀はもちろん、全国の忍者ゆかりの地には忍者屋敷がある。 忍者屋敷は外観は平屋造りで内部は三階建てになっていて、隠し部屋や抜け穴、落とし穴など、いろいろな工夫が凝らされている。 忍者はこの屋敷の隠し部屋で、火 … Continue reading
七方出
忍者は敵地に潜入する時、正体と目的を隠すために変装した。変装は、「虚無僧」「出家」「山伏」「商人」「放下師」(曲芸人)「猿楽師」「常の形」(農民や武士)の7つとされ、忍術伝書では「七方出で立ちの事」または「七化」と呼ば … Continue reading
「雪が降ると伊賀者が泣く」という言い伝え
春日局の頃にあった話です。家康の伊賀越えに功績があった伊賀・甲賀の忍を江戸城警備として徳川家は召し抱えました。そのうち甲賀者は大奥の外を、伊賀は大奥の内側の担当になりました。ところが外界から隔離された女の牢獄である大奥で … Continue reading
HOW TO WEAR AN IGA STYLE NINJA COSTUME
HOW TO WEAR AN IGA STYLE NINJA COSTUME how to wear(ninja)
役の行者
役行者小角、役優婆塞とも呼ばれる。「鬼神を思うままに使い、水くみや柴を採らせ、命に従わなければ呪術で縛って動けなくした」と噂され、遠流の罰に処された。 また、孔雀明王の呪法を修め、霊術を身につけ天を飛んだという話も残って … Continue reading
伊勢三郎義盛
【写真 伊勢三郎義盛の碑】 武蔵坊弁慶と並ぶ義経四天王の一人。 『正忍記』に源義経が忍びを使ったとある。これは伊勢三郎義盛一党のことと考えられる。別名、義経が会った時は、焼下小六という名で鈴鹿山の山賊頭領であった。 『伊 … Continue reading
比自山砦
【写真 比自山砦跡】 天正伊賀の乱では北伊賀の地侍達が立籠もり最も果敢に戦った比自山風呂谷の合戦は有名である。 『三国地志』には「比自山或いは愛宕山とも云う。観音廃堂の址あり、天正乱の時に本郡の処士に屯す」とある。 比自 … Continue reading
藤林保武
【写真 藤林保武の墓】 『萬川集海』の著者藤林佐武次保武は三代上忍の一人である藤林長門守の孫にあたる。 『冨治林家由緒家』によると、冨治林保武は東湯舟から上野万町に移り墓所が西念寺にある。別名は伝五郎、又の名を保道あるい … Continue reading
神戸ノ小南
【写真 神戸神社】 『萬川集海』に列挙された11人の忍術名人の1人。南伊賀では唯一の忍者であった。 文献としては菊岡如幻の『伊賀国忍術秘伝』、明和年間の岸勝明の『伊賀考』にも神戸の子南の名があるが活躍の記録としては文献に … Continue reading